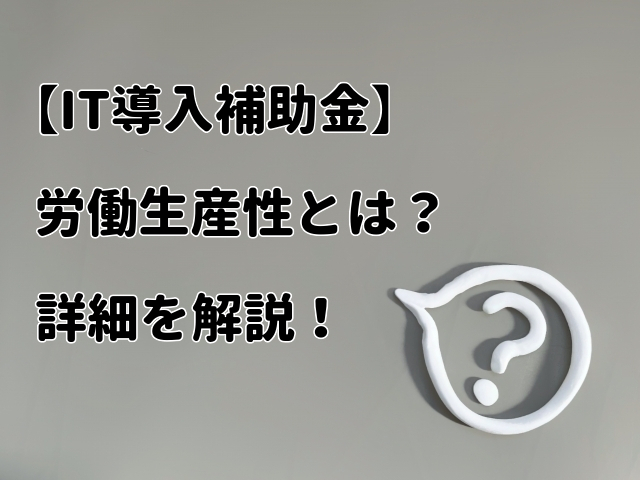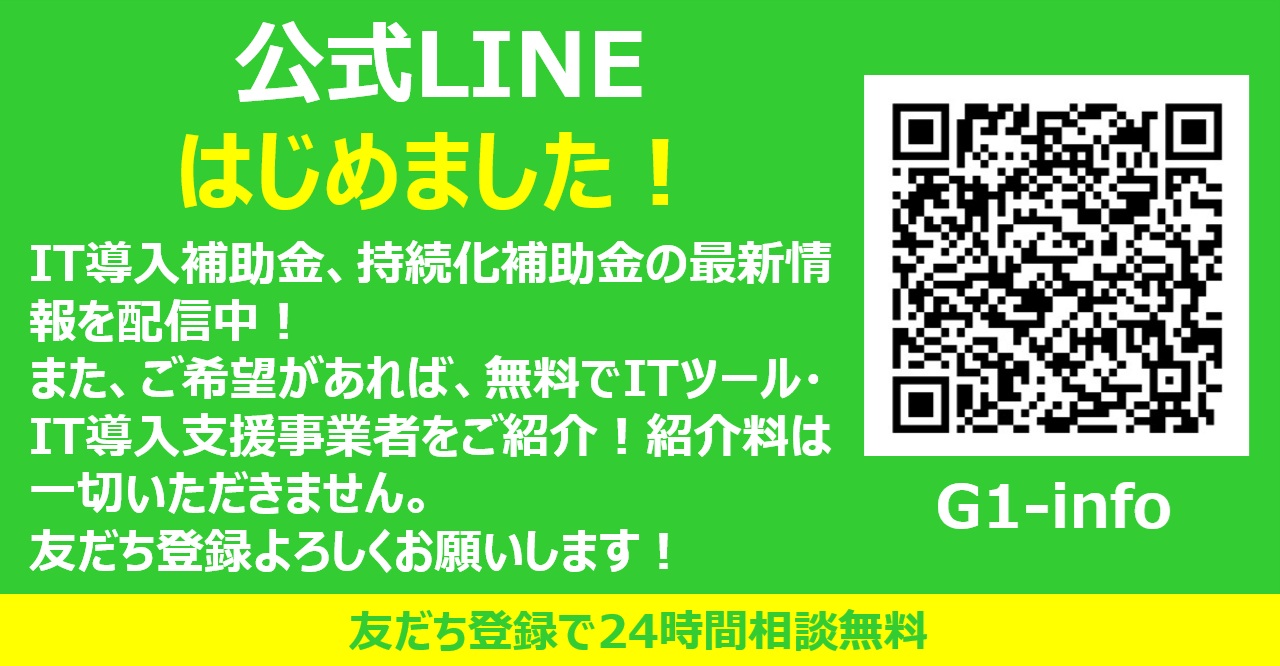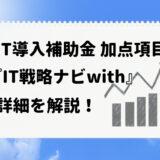IT導入補助金は、中小企業・小規模事業者等の労働生産性の向上を目指して、業務効率化やDX等に向けた ITツール(ソフトウェア、サービス等)の導入を支援する補助金制度ですが、この場合の「労働生産性」とは具体的にどういった意味になるのでしょうか。
この記事では、IT導入補助金における労働生産性の概要や計算方法、未達成だった場合のペナルティの有無などについて解説します。
※実際の申請に際しては、公募要領や交付申請の手引きを都度ご確認いただくようお願いいたします。
目次
労働生産性とは
生産性という言葉自体は、人・物・金・情報といった経営資源全体の効率を指す広い概念ですが、IT導入補助金における「労働生産性」とは、従業員1人が1時間でどれだけの利益(付加価値)を生み出すことができるかを示す指標です。
労働生産性の計算方法
IT導入補助金における労働生産性は、上述のとおり従業員1人あたりの時間単位の付加価値額と定義されており、付加価値額は以下の計算式で算出します。
付加価値額 = 営業利益 + 人件費 + 減価償却費
- 営業利益…売上から原価と販売費及び一般管理費を差し引いた額
- 人件費…給与手当、旅費交通費、賞与を合算した額
- 減価償却費…固定資産を法定耐用年数に応じて分割した費用
付加価値額を踏まえて、労働生産性の計算式は以下となります。
労働生産性 = 付加価値額 ÷(従業員数 × 1人当たりの年間平均労働時間)
つまり労働生産性を向上させるには、
■売上を増やすか、原価を下げる、もしくはその両方を行う
■従業員の労働時間を減らす
といった方法を取っていくことになり、IT導入補助金はこのような効果につながるITツールの導入支援を目的としているのです。
IT導入補助金で労働生産性が重要視されている理由
IT導入補助金はその目的に生産性向上を掲げていますが、なぜ労働生産性を重要視しているのでしょうか。
これは、中小企業や小規模事業者等の「稼ぐ力」を強化していく必要があるという国の意向があるためです。
中小企業や小規模事業者は、物価高や人手不足、最低賃金の引上げ、インボイス制度など新たな制度への対応など、事業環境を取り巻く変化への適応を強いられていますが、このような中でも安定的に収益力、つまり「稼ぐ力」を伸ばしていくためには、労働生産性の向上が不可欠です。
特に昨今の日本では最低賃金が毎年引上げられており、人件費もそれに比例して増加しています。
事業者がこの人件費の増加に対応しつつ、付加価値額を高めていくためには利益の拡大が必須ということになりますが、中小企業や小規模事業者はリソースやノウハウが足りていないことが多く、このバランスの維持が難しいという現状があります。
そこで、成長意欲のある中小企業や小規模事業者が労働生産性を向上させ、「稼ぐ力」を伸ばしていけるよう、デジタル化やDX等に向けたITツールの導入を支援しているのが、IT導入補助金になります。
ITツールの導入によって、売上の向上や業務効率が改善し、労働生産性を強化していくことで、中小企業や小規模事業者は利益を確保しながら、賃金引上げをはじめとした事業変化へ円滑に対応していけるようになるため、IT導入補助金では労働生産性の向上に重点が置かれているのです。
申請枠ごとの労働生産性の要件
IT導入補助金の通常枠、セキュリティ対策推進枠、複数社連携IT導入枠においては、労働生産性を向上させることが申請要件として定められており、労働生産性が向上していく事業計画を策定し申請時に提出する必要があります。
それぞれの枠の申請要件は次のように定められています。
通常枠
労働生産性について、以下の要件を全て満たす3年間の事業計画を策定し実行すること。
- 1年後に労働生産性を3パーセント以上向上させること。
ただし、IT導入補助金2022、IT導入補助金2023の通常枠(A・B類型)又はデジタル化基盤導入枠(複数社連携IT導入類型)若しくはIT導入補助金2024の通常枠又は複数社連携IT導入枠の交付決定を受けた事業者については、労働生産性を1年後に4パーセント以上向上させること。 - 事業計画期間において、労働生産性の年平均成長率を3パーセント以上とすること。
ただし、IT導入補助金2022、IT導入補助金2023の通常枠(A・B類型)又はデジタル化基盤導入枠(複数社連携IT導入類型)若しくはIT導入補助金2024の通常枠又は複数社連携IT導入枠の交付決定を受けた事業者については、労働生産性の年平均成長率を4パーセント以上とすること。 - 労働生産性の向上の目標が実現可能かつ合理的であること。
セキュリティ対策推進枠
補助事業者の事業全体における労働生産性(※)について、以下の要件を全て満たす3年間の事業計画を策定し実行すること。
- 事業計画期間において労働生産性の年平均成長率を1パーセント以上とすること。
- 労働生産性の向上の目標が実現可能かつ合理的であること。
※補助により軽減された負担分を振り向けた投資による効果、サイバー攻撃リスクの低減に伴う売上 損失の期待値減少効果、その他の経営努力による効果を含む。
複数社連携IT導入枠
補助事業グループの労働生産性について、以下の要件を全て満たす2年間の事業計画を策定し実行すること。
- 事業計画期間において労働生産性を年平均成長率5パーセント以上とすること。
ただし、IT導入補助金2023の通常枠(A・B類型)又はデジタル化基盤導入枠(複数社連携IT導入類型)若しくはIT導入補助金2024の通常枠又は複数社連携IT導入枠にて交付決定を受けた事業者が本事業のグループ構成員に含まれる場合、労働生産性を年平均成長率6パーセント以上とすること。 - 生産性向上の目標が実現可能かつ合理的であること。
なお、年平均成長率の算出については、 個々の参画事業者全ての労働生産性を求めた後、その結果を取りまとめ補助事業グループとしての幾何平均を求めること。上記により求めた値が、補助事業グループの労働生産性の年平均成長率とする。
通常枠とセキュリティ対策推進枠は3年間分の、複数社連携IT導入枠は2年間分の事業計画を申請時に策定する必要があります。
なお、インボイス枠については労働生産性向上の事業計画は求められません。
労働生産性の成長率が未達成だった場合
前述のとおり、IT導入補助金の多くの枠で労働生産性の成長率が定められていますが、これらを達成できなかった場合はペナルティなどがあるのでしょうか。
枠ごとに確認していきましょう。
通常枠・セキュリティ対策推進枠
通常枠・セキュリティ対策推進枠においては、規定の労働生産性の成長率が未達だった場合でもペナルティ等はありません。
そのため、補助金の返還義務等も発生しませんが、効果報告の際に計画数値未達の要因や、計画数値未達の改善方法等の報告が求められます。
ただし、そもそも申請した事業を実施していないことによる目標未達の場合は、補助金の交付そのものを取り消される可能性がありますので、注意しましょう。
複数社連携IT導入枠
複数社連携IT導入枠に関しても、労働生産性の成長率が規定数値に届かなかった場合の補助金の返還義務等は定められていません。
しかし、複数社連携IT導入枠で労働生産性の成長率が未達だった場合、以下のような措置が取られます。
- 事業計画期間において、労働生産性の年平均成長率が5パーセントに達しなかった場合(IT導入補助金2023の通常枠(A・B類型)又はデジタル化基盤導入枠(複数社連携IT導入類型)若しくはIT導入補助金2024の通常枠又は複数社連携IT導入枠にて交付決定を受けた事業者が、本事業のグループ構成員に含まれる場合は、事業計画期間において、労働生産性の年平均成長率が6パーセントに達しなかった場合)又は効果報告を行わなかった場合には、「補助事業名」「代表事業者名」「補助事業グループの構成員数」をホームページで公表する。
このように、複数社連携IT導入枠で労働生産性の成長率が事業計画に至らなかった場合は、その旨がIT導入補助金のホームページ上に公表される運びとなるため、当該申請枠を利用したい事業者はこの点を念頭に置くようにしましょう。
いずれの枠も補助金の返還義務等はありませんが、基本的には計画した数値の達成を目指して事業を行うようにしましょう。
まとめ
今回はIT導入補助金の労働生産性の概要や計算方法、未達成だった場合のペナルティの有無などについて解説しました。
事業の成長において労働生産性の向上は無視することのできないテーマになりますので、IT導入補助金の申請や採択決定後の事業実施の際には、ぜひ今回ご紹介した内容を意識して取り組んでみてください。
G1行政書士法人では、IT導入補助金開始当初から、多くの事業者様の申請支援を手掛けてきました。
4,500件以上の圧倒的な対応実績と専門知識をもとに、採択実現に向けた最適なサポートを提供しています。
IT導入補助金を利用したい中小企業・小規模事業者の方、ならびにITベンダー・サービス事業者の方は、ぜひ当法人までお気兼ねなくご相談ください。