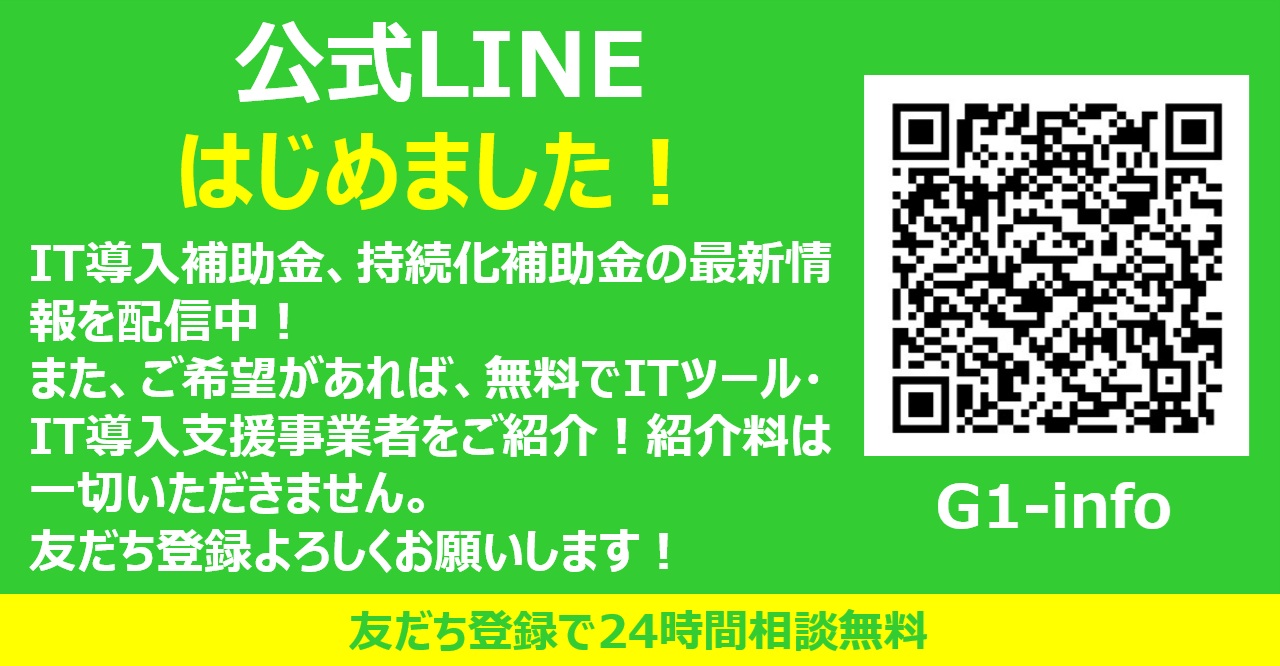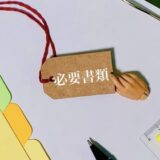2025年から新設された省力化投資補助金(一般型)は、現在第2回公募分までの採択結果が公表されています。
第2回公募分の採択結果は2025年8月8日に公表されましたが、採択率は60.9%と第1回公募分より低い採択結果でした。
本記事では、省力化投資補助金(一般型)の採択結果や採択率、ならびに審査を通過するためのポイントなどを解説していきます。
省力化投資補助金(一般型)の採択率
省力化投資補助金(一般型)の採択率は、以下のとおりです。
|
公募回 |
応募申請数 |
採択数 |
採択率 |
|
第1回 |
1,809 |
1,240 |
68.5% |
|
第2回 |
1,160 |
707 |
60.9% |
|
合 計 |
2,969 |
1,947 |
65.5% |
第2回の採択率は60.9%となり、第1~2回を合計した全体の採択率は65.5%の推移となりました。
第1回の採択率からは下がったものの、従前からの事業再構築補助金(近年の採択率25%~50%)、ものづくり補助金(近年の採択率30%~40%)などと比較すると、採択率が60%を超えている水準は、非常に採択率の高い補助金と言えます。
また、省力化投資補助金(一般型)では、採択結果とともに結果の概要をまとめた資料が公開されています。
この結果概要資料によると、第1回、第2回ともに採択件数に占める割合は「製造業」が1位(第1回:61.7%、第2回:58.4%)、「建設業」が2位(第1回:11.3%、第2回:12.4%)となっており、どちらの公募回もこの2業種だけで採択件数の7割超を占めている状況になっています。
これは製造業や建設業が「人材不足」と「熟練技術への依存」という構造的な課題を抱える業界であることや、その課題解決にオーダーメイド性の高い専用設備導入が効果的であること、設備導入による省力化の効果を数値で示しやすいことなどから、省力化投資補助金の目的にも合致して採択件数が多くなったと考えられます。
もちろん、製造業・建設業以外にも卸売業・小売業や学術研究、専門・技術サービス業、情報通信業など、多岐にわたる業種の事業者が採択されています。
どのような業種であっても、省力化投資による効果を明示できれば採択される可能性は十分ありますので、興味のある方はぜひチャレンジしてみましょう。
省力化投資補助金(一般型)審査通過のポイント
省力化投資補助金(一般型)の応募審査を通過するためには、いくつか押さえておきたいポイントがありますので、以下に代表的な内容を解説します。
省力化投資補助金(一般型)の対象要件を満たす
まず大前提として押さえておくべき点が、対象要件を満たす(対象外の要件に当てはまっていない)ことです。
「従業員数」や「資本金規模」などはわかりやすい対象要件ですが、公募要領で定められている「みなし大企業」や「みなし同一法人」の定義に該当する場合は、申請しても審査を通過することは難しいため注意が必要です。
また、以下のいずれかに該当する事業者は、省力化投資補助金(一般型)の申請対象外になります。
■過去に「ものづくり補助金」「事業再構築補助金」「新事業進出補助金」の交付決定を受け、応募申請時点で事務局からの補助金支払が完了していない事業者
■過去3年間に「ものづくり補助金」「事業再構築補助金」の交付決定を2回以上受けた事業者
「せっかく準備したのに申請対象外だった」という事態を避けるためにも、着手する前にまずは公募要領をしっかり確認するようにしましょう。
可能な限り加点項目に取り組む
省力化投資補助金(一般型)では、審査で加点となる項目が公募要領で公開されていますので、応募申請の際は、できる限り加点項目に取り組むことが望ましいです。
省力化投資補助金(一般型)第4回公募の加点項目は以下のとおりです。
- 過去3年以内に事業承継(株式譲渡等)により有機的一体としての経営資源(設備、従業員、顧客等)を引き継いでいる事業者
- 有効な期間の事業継続力強化計画(連携型含む)の認定を取得している事業者
- 応募締切日時点で「成長加速マッチングサービス」において会員登録を行い、挑戦課題を登録している事業者
- 事業計画期間了時点における給与支給総額の年平均成長率4.0%以上増加する計画を有すること及び、事業場内最低賃金を毎年3月に事業実施都道府県における最低賃金より+40円以上の水準を満たすことを目標とし、事務局に誓約している事業者
- 2024年10月から2025年9月までの間で、「当該期間における地域別最低賃金以上~2025年度改定の地域別最低賃金未満」で雇用している従業員が全従業員数の30%以上である月が3か月以上ある事業者
- 2025年7月と応募申請直近月の事業場内最低賃金を比較し、「全国目安で示された額(63円)」以上の賃上げをした事業者
- 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)に基づく「えるぼし認定」を受けている事業者
- 次世代育成支援対策推進法(次世代法)に基づく「くるみん認定」を受けている事業者
なお、4.の賃上げに関する加点を受けた事業者が、賃上げの要件を未達成だった場合は、次のようなペナルティが生じますので注意しましょう。
■補助事業を完了した事業年度の翌年度以降、事業計画期間終了時点において給与支給総額又は1人当たり給与支給総額の増加目標が未達だった場合、達成率の高い目標値の未達成率を乗じた額の返還を求められます。
■補助事業を完了した事業年度の翌年度以降、事業計画期間中の毎年3月末時点において、事業場内最低賃金の引き上げ要件が達成できていない場合は、補助金額を事業計画年数で除した額の返還を求められます。
※上記いずれも、付加価値額が増加しておらず、かつ企業全体として当該事業年度の営業利益赤字の場合などや天災など、事業者の責めに帰さない理由がある場合は、上記の補助金返還を求められません。
■賃上げが未達となった旨の報告をしてから18か月間、当該補助金の次回公募及び中小企業庁が所管する他の補助金への申請において、正当な理由が認められない限り大幅に減点されます。
事業計画書を入念に作り込む
省力化投資補助金(一般型)では、申請内容の妥当性や具体性が大きな判断材料となるため、それらが伝わるような事業計画書を入念に作成することが重要です。
具体的には、以下のようなポイントを踏まえた事業計画書作成が大切です。
■「労働生産性の年平均成長率+4.0%以上増加」などの基本要件を満たした数値計画を作成する
■「人的リソース不足」「作業が属人化している」「アナログ作業の常態化」「ヒューマンエラーの多発」など、客観的にわかりやすい課題がある旨を説明する
■導入する設備や申請金額が妥当であることを示す
■「省人化」「作業時間削減」「品質の均一化」「新たな付加価値の創出」といった設備投資による省力化の成果を数値で提示する
■設備投資をした後の展望(「人的リソースの見直しによる事業拡大」「収益性の改善」など)まで明示する
事業計画書は、認定支援機関などの専門家へ作成支援を依頼することで、要件やポイントを押さえた事業計画書の作成が可能となりますので、「自分で事業計画書を上手く作れる自信がない」という方は、専門家の活用をおすすめします。
まとめ
今回の記事では、省力化投資補助金(一般型)の採択結果や採択率、ならびに審査を通過するためのポイントなどを解説しました。
今後も採択結果が発表されるごとに、随時情報を更新していきます。
当サイトを運営するG1行政書士法人は、IT導入補助金をはじめとする各種補助金申請におけるサポートを幅広く提供しており、省力化投資補助金においても認定経営革新等支援機関(認定支援機関)として、事業計画書作成支援や代理申請、申請フォローなどに対応しています。
事業計画書作成や補助金申請書作成など累計4,500件を超える実績と豊富なノウハウ、専門家としてのナレッジを活用してサポートを提供していますので、省力化投資補助金を申請したい中小事業者の方や、顧客に対し自社製品を販売する際、省力化投資補助金の活用を薦めたいと考えている販売業者の方はお気軽にお問い合わせください。