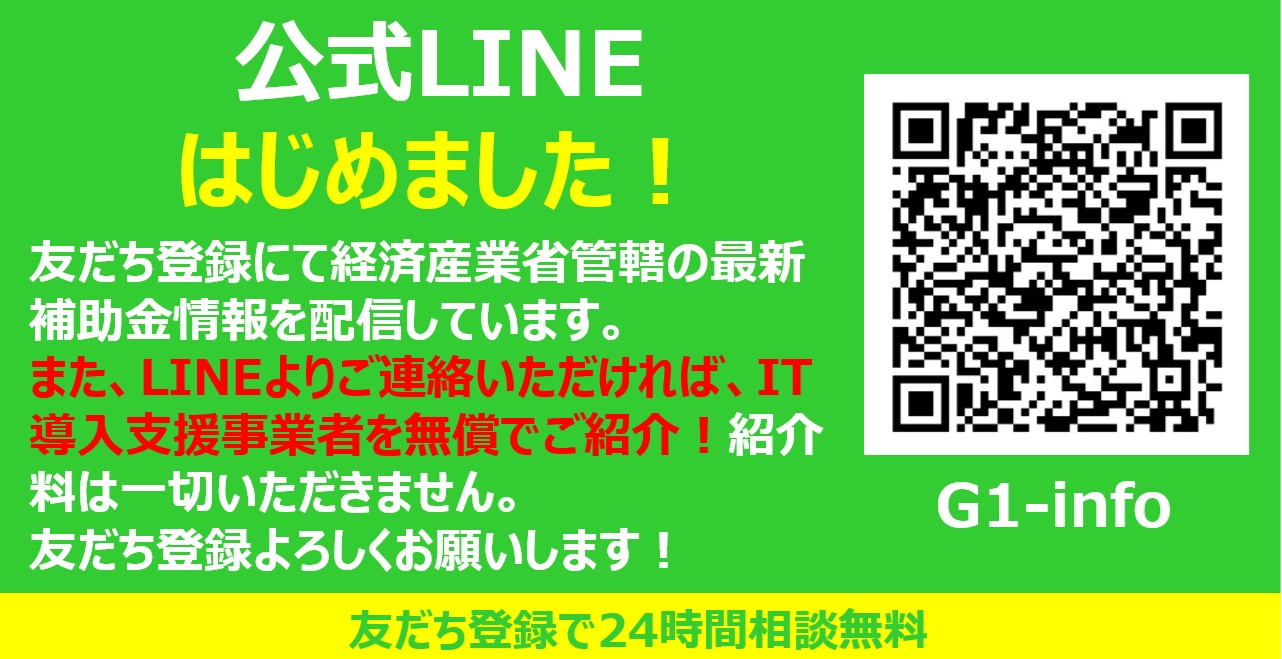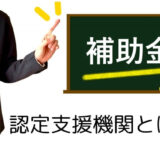省力化投資補助金(一般型)はその事業目標に賃上げを掲げており、基本要件でも給与支給総額や事業場内最低賃金の向上など、賃上げに取り組むよう定められています。
また、基本要件よりも更に高い賃上げに取り組むことで補助上限額の引き上げが適用されたり、加点を受けたりすることも可能になりますが、「賃上げについての要件が複雑でよくわからない」という事業者の方もいるのではないかと思います。
そこで今回は、省力化投資補助金(一般型)における賃上げ目標の概要をはじめ、給与支給総額の定義やその中に役員報酬は含まれるのか、ならびに未達となった場合のペナルティなどについて解説していきます。
※本記事は第4回公募回時点での情報をもとに記載していますので、実際の申請にあたっては必ず最新の公募要領や手引き等をご確認ください。
目次
賃上げ要件とは
賃上げ要件とは、省力化投資補助金(一般型)に申請する事業者が自ら設定する賃金引き上げの目標です。
詳しい数値などに関しては後述しますが、省力化投資補助金(一般型)では
●給与支給総額、又は1人当たり給与支給総額を増やすこと
●事業場内最低賃金を上げること
の2点が求められます。
賃上げに関する取り組みが審査項目に含まれているのは、省力化投資補助金(一般型)が人手不足に直面している中小企業等の付加価値額増加や、生産性向上を目的としているためです。
つまり、「省力化設備の導入によって業務効率を高め、限られた人員で付加価値額や生産性の向上を達成できるようにする⇒その成果を従業員の給与に還元してもらうことで、経済の活性化を図りたい」
という国の考えが背景にあるため、省力化投資補助金(一般型)では賃金引き上げへの取り組みが求められているのです。
賃上げの取り組み内容
省力化投資補助金(一般型)では、賃上げへの取り組みが基本要件として定められています。
そのため、省力化投資補助金(一般型)に申請する際は、賃上げ対応が必須ということになりますので、申し込みを検討している場合はこの点をきちんと認識しておくようにしましょう。
また、基本要件とは別で定められている賃上げ項目に取り組むことで、補助上限額が引き上がる特例措置を受けられたり、審査で加点となる場合もあります。
以下、事業者が必須で取り組む必要がある基本要件と、補助上限額引き上げのための特例措置に関する要件、ならびに加点を受けるための要件について解説します。
基本要件
省力化投資補助金(一般型)の賃上げに関する基本要件として、全ての申請者は次の要件を満たす3~5年の事業計画を策定し、達成することが求められます。
この賃上げに関しては、省力化投資補助金(一般型)に申請する全ての事業者が取り組む必要がありますので注意しましょう。
①給与支給総額を年平均成長率+2.0%以上、又は1人当たり給与支給総額の年平均成長率が事業実施都道府県における最低賃金の直近5年間の年平均成長率以上増加させる
※給与支給総額と、1人当たり給与支給総額の詳細については後述します。
②事業場内最低賃金を事業実施都道府県における最低賃金+30円以上の水準にする
応募申請時は「給与支給総額」と「1人当たり給与支給総額」それぞれの目標値を設定する必要があり、効果報告の際も同じく両方の実績を報告します。
この際、「給与支給総額」または「1人当たり給与支給総額」のどちらか一方の目標を達成していることが求められます。
いずれの目標も達成できなかった場合は、達成率に応じて補助金を返還する必要があります。
特例措置要件
以下の2点の大幅な賃上げ要件を満たした事業計画書を作成し、取り組む事業者は、補助上限額の引き上げ措置を受けることができます。
①事業計画期間終了時点において、基本要件である給与支給総額を年平均成長率+2.0%以上増加させることに加え、更に年平均成長率+4.0%以上(合計で年平均成長率+6.0%以上)増加させる事業計画を策定し、採択を受けた場合は自身が設定した目標値を達成させること。
②事業計画期間において、事業場内最低賃金(補助事業を実施する事業場内で最も低い賃金)を事業実施都道府県における最低賃金+50円以上の水準とすること。
引き上がる補助上限額は従業員の数に応じて決まります。
ただし、常勤従業員がいない場合は当該特例措置を受けることはできませんので注意しましょう。
|
従業員数 |
補助上限額の引き上げ額 |
引き上げ後の補助上限額 |
|
5人以下 |
申請枠の上限から+250万円 |
1,000万円 |
|
6~20人 |
申請枠の上限から+500万円 |
2,000万円 |
|
21~50人 |
申請枠の上限から+1,000万円 |
4,000万円 |
|
51~100人 |
申請枠の上限から+1,500万円 |
6,500万円 |
|
101人以上 |
申請枠の上限から+2,000万円 |
1億円 |
加点要件
以下のいずれか、または両方の賃上げ目標に取り組む事業者は、審査において加点の対象となります。
①事業計画期間終了時点での給与支給総額の年平均成長率を4.0%以上増加させることと、事業場内最低賃金を毎年3月に事業を実施する都道府県における最低賃金より+40円以上の水準にすることを目標とし、かつ事務局に誓約すること
②2025年7月と応募申請直近月の事業場内最低賃金を比較し、「全国目安で示された額(63円)」以上の賃上げをすること
※②は第4回公募から追加された加点項目になりますが、従業員がいない事業者の場合は対象外となります。
給与支給総額・1人当たり給与支給総額
「給与支給総額と1人当たり給与支給総額って何が違うの?」と思う方もいるのではないでしょうか。
給与支給総額と1人当たり給与支給総額には、次のような違いがあります。
給与支給総額とは
給与支給総額とは、応募申請時及び最終年度のそれぞれの時点で就業している従業員(役員を含む)に対して支払われた給与等の合計額のことを言います。
算定の対象となるのは、以下のような給与所得として課税対象となる経費です。
●給料・賃金
●役員報酬
●賞与(ボーナス)
●各種手当(残業手当、休日出勤手当、職務手当、地域手当、家族(扶養)手当、住宅手当など)
一方で、以下は給与支給総額には含まれません。
●福利厚生費
●法定福利費
●退職金
1人当たり給与支給総額とは
1人当たり給与支給総額とは、対象となる従業員分の給与支給総額を、対象従業員数で割った金額のことを言います。
対象となる従業員は、応募申請時から事業計画最終年度まで継続して就業している「同一人」となります。
この「同一人」とは、応募申請時及び事業計画期間(3~5年の各事業年度末)に、全月分の給与等の支給を受けた従業員を意味します。
よって、中途採用や退職などにより、応募申請以降の全月分の給与等の支給を受けていない従業員は、1人当たり給与支給総額の算定対象から除外されます。
算定に含まれるのは、以下のような給与所得として課税対象となる経費です。
●給料・賃金
●賞与(ボーナス)
●各種手当(残業手当、休日出勤手当、職務手当、地域手当、家族(扶養)手当、住宅手当など)
一方で、福利厚生費・法定福利費・退職金は算定に含まれません。
また、産前・産後休業、育児休業、介護休業など事業者の福利厚生等により時短勤務を行っている従業員も、算定対象から除外することが可能です。
なお、応募申請時点で従業員がいない場合、または応募申請時から最終年度まで継続して就業している「同一人」がいない事業者の場合は、1人当たり給与支給総額ではなく「給与支給総額」の目標値を用いることになります。
役員報酬は含まれる?
「給与支給総額や1人当たり給与支給総額を向上させるにあたって、役員報酬を引き上げる形でも良いのか」という質問を当法人でも頂くことがあります。
この点については、給与支給総額には役員報酬も含まれるため、上記対応も可能となります。
一方、1人当たり給与支給総額のカウントには、役員も役員報酬も含まれません。
上述のとおり1人当たり給与支給総額は、対象となる従業員分の給与支給総額を対象従業員数で割った額のことを指しますが、ここの対象となる従業員に役員は含まれないため、役員報酬等を除外した金額で計算することになります。
例えば、役員1人、従業員2人の会社で、役員報酬が100万円、給与手当が600万円の場合、次のような計算になります。
<給与支給総額の計算>
100万円(役員報酬)+600万円(給与手当)=700万円
<1人当たり給与支給総額の計算>
600万円(給与手当)÷2人(役員を除いた従業員数)=300万円
省力化投資補助金(一般型)に申請する場合は、この違いを認識しておく必要があります。
賃上げ目標の表明方法
賃上げ目標の数値は、特例措置や加点に取り組むかなどにより異なってきますが、いずれの場合も策定した目標値と賃上げを行う旨を、交付申請時までに全ての従業員又は従業員代表者、役員に対して表明する必要があります。
表明は「社内掲示板等への掲載」「朝礼時等に口頭での周知」「書面の配布」「メール」等、任意の方法で問題ありません。
また、従業員へ表明した内容は「賃金引き上げ計画の表明書(指定様式)」として交付申請時に提出する必要があります。
この書類は従業員を雇用していない代表者1名のみの事業者の場合も提出が必要となりますので、一人会社の方なども認識しておくようにしましょう。
賃上げ目標未達の場合のペナルティ
省力化投資補助金(一般型)で賃上げ目標が未達だった場合、ペナルティが発生するため注意が必要です。
ペナルティは取り組む内容によって次のとおり異なります。
基本要件
■給与支給総額又は1人当たり給与支給総額の増加目標が未達の場合
補助事業を完了した事業年度の翌年度以降、事業計画期間終了時点で、給与支給総額又は1人当たり給与支給総額の目標数値をいずれも達成できなかった場合は、達成率に応じて補助金の返還を求められ、達成率が高い目標値に未達成率をかけた額を返還する必要があります。
※ただし、付加価値額が増加しておらず、かつ企業全体として事業計画期間の過半数が営業利益赤字の場合などや天災など、事業者の責めに帰さない理由がある場合は、補助金返還が求められない旨が公募要領で示されています。
<達成率の計算方法>
①給与支給総額の達成率 =(事業計画終了時点の給与支給総額の年平均成長率(%))÷(申請時に掲げた2.0%以上の目標値(%))
②1人当たり給与支給総額の達成率 =(事業計画終了時点の1人当たり給与支給総額の年平均成長率(%)÷(申請時に掲げた各都道府県別の基準率以上の目標値(%))
<返還金額の計算方法>
上記の達成率①と②を比較し、①が高い場合は③、②が高い場合は④で算出した金額を返還する必要があります。
③給与支給総額の場合の返還金額 =(補助金交付額-補助上限引き上げ額)×(1-給与支給総額の達成率)
④1人当たり給与支給総額の場合の返還金額 =(補助金交付額-補助上限引き上げ額)×(1-1人当たり給与支給総額の達成率)
■事業場内最低賃金の引き上げ要件が未達の場合
補助事業を完了した事業年度の翌年度以降で、事業計画期間中の毎年3月末時点で事業場内最低賃金の引き上げ要件が達成できていない場合は、補助金額を事業計画年数で割った金額の返還が求められます。
※ただし、付加価値額が増加しておらず、かつ企業全体として当該事業年度の営業利益が赤字の場合などや天災など、 事業者の責めに帰さない理由がある場合は、補助金返還が求められない旨が公募要領で示されています。
特例措置要件
大幅賃上げに係る補助上限額引き上げの特例措置要件の申請は、以下のいずれか一方でも未達の場合、補助金交付金額から従業員数ごとの補助上限額との差額分を返還する必要があります。
①事業計画期間終了時点において、給与支給総額の年平均成長率を6%以上増加させる
②補助事業を完了した事業年度の翌年度以降、事業計画期間中の毎年3月末時点において、事業場内最低賃金を都道府県の最低賃金+50円以上の水準にする
加点要件
賃上げ加点の申請は、効果報告の際に加点要件となる賃上げ目標が未達の場合、次のようなペナルティが発生します。
①「給与支給総額の年平均成長率を4.0%以上増加」又は「事業場内最低賃金を毎年3月に事業を実施する都道府県における最低賃金より+40円以上の水準にする」が未達の場合、「基本要件未達の場合の補助金返還義務」に基づいた返還(達成率に応じた補助金の返還又は補助金額を事業計画年数で割った金額の返還)が求められます。
②上記の賃上げ目標が未達となった旨の報告をしてから18か月間、省力化投資補助金(一般型)の次回公募及び中小企業庁が所管する他補助金(※)への申請において、正当な理由が認められない限り大幅に減点されます。
※2025年9月時点の「他補助金」は以下が公表されています。
ものづくり・商業・サービス生産性向上促進事業(ものづくり補助金)
サービス等生産性向上IT導入支援事業(IT導入補助金)
小規模事業者持続的発展支援事業(持続化補助金)
事業承継・M&A支援事業(事業承継・M&A補助金)
中小企業等事業再構築促進事業(事業再構築補助金)
中小企業省力化投資補助事業(省力化投資補助金)
中小企業新事業進出促進事業(新事業進出補助金)
まとめ
今回は省力化投資補助金(一般型)の賃上げ目標の概要や、役員報酬は給与支給総額に含まれるのか、未達だった場合のペナルティなどについて解説しました。
全申請者賃上げに取り組むことが基本要件となっていますが、追加で賃上げすることによる加点や、補助上限額の引き上げ特例措置など、優位な条件にできる措置も用意されています。
ただし、賃上げ目標が未達成だった場合は、補助金の返還など厳しいペナルティもありますので、事業者ごとの状況に応じた計画や取り組みが重要です。
当サイトを運営するG1行政書士法人では、IT導入補助金や持続化補助金など、累計4,500件以上の補助金申請のサポートを提供してきました。
また、認定経営革新等支援機関(認定支援機関)の認定も受けているため、省力化投資補助金(一般型)の事業計画書作成支援や代理申請、申請時のフォローにも対応しております。
専門家としての知見と積み重ねたノウハウを最大限活用した支援が可能ですので、「省力化投資補助金を活用してみたい!」とお考えの中小事業者の方や、「自社製品を販売する際、省力化投資補助金の活用をお客様に推奨したい」という販売業者の方は、お気軽にお問い合わせください。